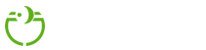本文
発掘されたご先祖様の足跡 谷ノ台遺跡、小谷遺跡
袖ケ浦市内には、500箇所を超える昔の人々が暮らしたムラの跡や、古墳があることがわかっています。
その中には、やむを得ず現地に残すことができない遺跡については、「発掘調査」によって記録されています。
生涯学習課では、過去の発掘調査で発見され、保管されている出土品を多くの方々が利用しやすくなるよう、出土品の再整理を行っています。
令和元年度(2019年度)に再整理を行った、谷ノ台遺跡、小谷遺跡の2遺跡を紹介します。
谷ノ台遺跡(やつのだいいせき)-弥生時代と江戸時代のお墓が見つかった遺跡―
谷ノ台遺跡は袖ケ浦市神納に所在し、小櫃川下流域の北側台地標高約32mに位置しています。
当遺跡は主に市道0102号線(平成通り)建設工事にともない、平成4~6年度にわたり調査された区域です。
発見した生活跡は弥生時代後期から古墳時代前期(約3世紀から4世紀)の住居、弥生時代中期から後期(紀元前約1世紀から紀元3世紀)の方形周溝墓、古墳時代後期の古墳(約6世紀)、奈良・平安時代方形区画墓・土壙基(約9世紀から14年前)、江戸時代後期(約塚などがあり、長い時代にわたり墓地の性格が強い遺跡ということがわかりました。
出土した主な生活道具には、壺・甕・鉢・器台・高坏・陶器・磁器・和鏡などを発見することができました。
小谷遺跡(こやついせき)-弥生時代と平安時代のムラが営まれた場所―
小谷遺跡は、袖ケ浦市永吉に所在し、小櫃川下流域の北側台地標高約55mに位置しています。遺跡は、土砂採取事業にともない、平成2年度に調査されました。
発見した生活跡は、主に住居跡で弥生時代中期(紀元1世紀前半頃)9軒、平安時代(9世紀後半から10世紀前半頃)16軒です。
弥生土器(壺(つぼ)・甕(かめ)・甑(こしき)・鉢(はち))、土師器(はじき)(坏(つき)・椀(わん)・台付坏(だいつきつき))・須恵器(すえき)(坏・皿・甕・甑・長頸(ちょうけい)壺(こ))などの生活道具が発見されています。
土器の様相から、当遺跡は短い時期にわたり小規模な単位の村として営まれていたことがわかりました。