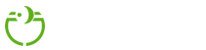本文
後期高齢者医療制度の給付
医療機関で支払う自己負担割合
後期高齢者医療の自己負担割合は前年の所得状況により、下記の所得区分に分けられ、1割、2割、3割のいずれかとなります。
なお、自己負担割合の判定は毎年8月に行います。
| 自己負担 の割合 |
所得区分 | 判定基準(令和7年8月1日~令和8年7月31日) |
|---|---|---|
| 3割 |
現役並み所得者3 |
市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 |
| 現役並み所得者2 | 市町村民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 | |
| 現役並み所得者1 | 市町村民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 | |
| 2割 |
一般2 |
市町村民税課税所得28万円以上 |
| 1割 | 一般1 | 市町村民税課税所得28万円未満 ※住民税が課税されている世帯 |
| 区分2 (低所得者2) |
世帯の全員が市区町村民税非課税のかた(区分1以外の被保険者) | |
| 区分1 (低所得者1) |
○世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80.67万円で計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる被保険者 ○世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給しているかた |
※現役並み所得者であっても、
世帯内の被保険者の収入額が一人の場合で383万円以下または383万円以上であるが、同一世帯の70歳から74歳までのかた全員の収入を含めた収入の合計金額が520万円未満、
世帯内に被保険者が二人以上の場合で520万円以下である場合は申請することで1割または2割負担に変更できます。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
|
自己負担割合 |
所得区分 |
食費(一食当たり) |
|
|---|---|---|---|
|
3割 |
現役並み所得者 |
510円(※1) |
|
|
2割 |
一般2 |
||
| 1割 | 一般1 | ||
|
区分2 |
過去12か月の入院日数が90日まで |
240円 |
|
|
区分2 (長期該当※3) |
過去12か月間の入院日数が91日以上 |
190円 |
|
|
区分1 |
140円または110円 |
||
※1 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円。
※2 一部医療機関では470円
※3 区分2に該当し、過去12か月で入院日数が91日となったときは、入院日数のわかる領収書等を添えてご申請ください。なお、申請月の翌月初日から有効となります。
医療費が高額になったときは
1か月間(同じ月内)に自己負担した医療費が高額になった場合、申請することにより、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
(申請は一度していただければ、次回以降は不要です。) ※入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用外の費用は含みません。
自己負担限度額(月額)
| 自己負担割合 | 所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〇多数回該当(※1)の場合は140,100円 |
|
| 現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〇多数回該当(※1)の場合は93,000円 |
||
| 現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〇多数回該当(※1)の場合は44,400円 |
||
| 2割 | 一般2 |
6,000円+(医療費-3万円)×10% または、18,000円の いずれか低い方を適用(※2) 〇年間(8月~翌年7月) 144,000円上限 |
57,600円 〇多数回該当(※1)の場合は44,400円 |
| 1割 | 一般1 |
18,000円 〇年間(8月~翌年7月) 144,000円上限 |
|
| 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分1 | 8,000円 | 15,000円 | |
※1:多数回該当とは、直近12か月以内に、3回以上世帯単位の高額療養費が該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。
※2:窓口の負担割合が2割のかたは、負担を抑えるための配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。1か月の外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
厚生労働大臣が指定する特定疾病患者の場合
高額な治療を長期間継続して行う必要がある、下記の疾病に係る医療を受けている方は、申請により交付される「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、毎月の自己負担限度額が10,000円までとなります。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
その他の医療費の支給
以下のような場合は、医療費の全額を自己負担し、後から療養費を申請すると自己負担分を除いた金額が支給されます。
- 不慮の事故などのやむを得ない理由により、医療機関等にて資格確認書等を提示せず受診した場合や保険医療機関以外等で医療等を受けた場合(海外旅行中に医療を受けた場合を含む)
- 医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具(補装具)を購入した場合
- 医師が必要と認めたはり・きゅう、あんま・マッサージを受けた場合
- 骨折やねんざ等で保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
人間ドック費用助成
後期高齢者医療制度の加入者を対象に、人間ドックにかかる費用の一部を補助しています。
契約医療機関のみ対象です。
(契約医療機関は必要に応じて追加することが出来ます。ただ、契約をする必要があるので、ご要望の医療機関がありましたら、お早目にお知らせください。)
1.契約医療機関
国民健康保険の契約医療機関と同じです。(国保の人間ドック費用助成のページはこちらから)
2.補助対象者の要件
- 袖ケ浦市に住所を有する、後期高齢者医療の加入者であること。
- 現に加療中の場合、ドック受検に支障がないこと。
- 年度内に、この補助を受けていないこと。
- 納期限の到来している後期高齢者医療保険料を完納していること。
- 年度内に後期高齢者健康診査を受けていないこと。
3.助成金額
助成額は一律20,000円です。
※検査費用が上記金額に満たない場合、助成額は検査費用相当額となります。
4.手続き
- 医療機関で検査希望日を予約します。
- 検査日の14日前までに、市役所保険年金課または、各行政センターの窓口で人間ドック利用申請書を提出します。
- 申請書確認後、利用承認書が受検者へ送付されます。
- 利用承認書を持参して検査を受けます。
- 医療機関の窓口で、助成額を差し引いた額を支払います。
高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯内で、後期高齢者医療制度・介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月から翌年7月まで)で合算し、下表の限度額を超えた額が、申請により支給されます。
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度 + 介護保険の自己負担限度額(年額) |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 | 141万円 |
| 現役並み所得者1 | 67万円 |
| 一般2 | 56万円 |
| 一般1 | |
| 区分2 | 31万円 |
| 区分1 | 19万円 |
※区分1で世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額が異なる場合があります。
医療費の一部負担金の減免
震災、風水害、火災等で大きな損害を受けたとき、また事業の休廃止などで所得が激減したことにより、病院などの窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請することで一部負担金の免除・減額または支払いの猶予を受けられる制度があります。
詳しくは下記のページをご参照ください。