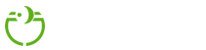本文
令和6年度 災害「避難」を学ぶ講座を開催しました
いつ訪れるかわからない災害時の避難生活を見すえて、各々がどうしたらよいか、何ができるかを学び、避難所生活を余儀なくされた場合、周囲と協力し合える人材の育成と、地域の連帯感の醸成を目指します。
| 回 | 開催月日・時間 | 内容 | 開催場所等 |
|---|---|---|---|
| 第1回 |
5月18日(土曜日) 10時00分~11時30分 |
命を守る防災 -平常時の備えを考える- |
視聴覚室 |
| 第2回 |
5月23日(木曜日) 18時30分~20時00分 |
||
| 第3回 |
7月13日(土曜日) 10時00分~11時30分 |
車椅子対応型トイレを組立ててみよう! | 多目的室 |
| 第4回 |
9月2日(月曜日) 13時00分~15時00分 |
平川中学校避難訓練見学と(1)避難所開設訓練または(2)救命講習(中学校家庭教育学級 共催)※台風のため中止 |
平川中学校 |
| 第4回(延期) |
3月13日(木曜日) 12時50分~15時00分 |
平川中学校避難訓練見学と避難所開設訓練 (中学校家庭教育学級 共催) |
平川中学校 |
|
10月5日(土曜日) 10時00分 ~ 12時00分 |
災害時に役立つパッククッキング体験 |
調理実習室 |
|
| 第6回 |
2月2日(日曜日) 9時00分~11時40分 |
避難所を確認する ※市総合防災訓練参加 |
全館 |
第1回・第2回 命を守る防災-平常時の備えを考える-
5月18日(土曜日)午前中と23日(木曜日)夜間に、災害「避難」を学ぶ講座の「命を守る防災-平常時の備えを考える-」と題した講演会を開催しました。
今回は、改めて、多くの方に「いざ」というときのための備えの考え方をお伝えしようと、中富地区には3月から先行してチラシを回覧し、他は市の広報やLINEを活用してPRしたほか、平川交流センターで活動されている方等への周知強化も試み、おかげさまで多くの方の年間講座登録をいただくことができました。
講師は、平川公民館顧問が務めましたが、自身で撮影した震災後の写真や動画を交え、物や室内外への備え等、平常時から心がけておくことをお話ししました。
日頃から訓練や備え、心がけをしておくことがいかに重要か、また、自分の置かれた環境によって、ケースバイケースで備え考えることが大切だとの学びが得られる内容となりました。23日は、臨場感のある停電体験も行いました。

第3回 車椅子対応型トイレを組立ててみよう!
実際に即して行うということで、特に講師は招かず、自分たちの力でやれるところまでやってみる、という趣旨で行いました。出来上がりがかなり大きなものになるため、部品の扱いが難しく、組立ての順番も複雑で、皆で大変苦労して、一応きりの良いところまで組上げ、崩して、全員で箱に戻すところまで行うことができました。
担当の社会教育推進員や参加者が、参考にと自身で購入した段ボールトイレ等を持ってくるして見せてくれましたが、いざという時の各々の備えの大切さも、同時に実感できました。

第4回(延期) 平川中学校避難訓練見学と避難所開設訓練
第3回平川中学校家庭教育学級と合同で、平川中学校の避難訓練と併せて、1年生には避難所開設訓練、2年生には止血法等消防署による講習を企画し、家庭教育学級生と災害「避難」を学ぶ講座生は、1年生と一緒にパーテーションや段ボールベッドの資器材組立て作業を行いました。
最初に、生徒が地震により校庭へ避難する様子を見学しましたが、指示に従い、まとまって素早かったのが印象的でした。
その後の資器材組立て作業も、講師を務めた防災安全課職員の説明を聞いて、5人くらいの班で組立てを行いましたが、学級生や講座生からは、その様子が大変頼もしかったと感想がありました。
避難所である地域の学校に保護者をはじめ地域の大人が行き、様子を見たり、一緒に作業したりすることができて、大変意義のある内容となりました。






第5回 災害時に役立つパッククッキング体験
調理実習と「災害時の食事作りと簡単活用方法」についての講話を行いました。
今回は親子丼のパッククッキングでした。お米を袋に入れ、お湯で炊くところから、具には缶詰の鶏肉を使用し、玉子も湯煎で程よい硬さに仕上げ、本当に美味しく出来上がりました。
これならいざという時でも、安心して温かい美味しいご飯が食べられ元気も出ると、ご参加の皆さんにも大変好評でした。そして、そのためにも、日頃の備えが大切であることが分かった回となりました。

第6回 避難所を確認する
令和6年度市総合防災訓練(平川交流センター(平川公民館)会場)に参加しました。
市では、地震等の大規模災害に備え、市及び関係機関が連携し、地域住民と一体となって行う訓練として、総合防災訓練を行っています。
平川交流センター(平川公民館)会場では、パーテーションや段ボールベッドの組立て体験や体育室に居住区画をつくる体験、物資の配布体験やトイレが停電し、流すことができなくなった場合を想定しての体験など、グループに分かれて各体験を行ったり、体験で設置などした成果を全員で見て回ったりしました。
その後は、地域でボランティアとして防災や災害対応への啓発や訓練を行っている災害対策コーディネーター連絡会の方からPRをしていただきました!なぜ災害対策コーディネーターになろうと思ったか、連絡会はどんな組織か、どんな活動を行っているかを、わかりやすく、熱く語っていただき、より一層、地域の防災意識向上につながったかと思います。