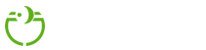本文
田んぼの学校【市内小学校】 実施報告2025
稲刈り
黄金色に輝く稲穂と、賑やかな稲刈り体験
農村公園ひらおかの里の田んぼでは、4月と5月に植えられた苗が順調に育ち、黄金色の稲穂が頭を垂れる季節となりました。
今年の夏も猛暑でしたが、9月2日から9月11日までの間、熱中症に注意しながら、小学校の児童405名による賑やかな稲刈りがおこなわれました。
この稲刈りでは、児童たちにとって初めての体験となる、鎌を使った手刈りと「おだ掛け」による天日干しを体験しました。まず、刈った稲を束ねるための「スガイ」を、稲わらをねじって縄状にする作業から始めました。スガイを腰に巻き付け、鋸鎌(のこぎりかま)を手に田んぼに入ります。稲を6株ほど刈り、スガイの上に根元側を置いた後、さらに6株ほどを先に置いた稲と交差させて重ね、スガイで束ねていきます。この作業を繰り返し、田んぼ一面の稲を刈り取りました。
次に、束ねた稲を天日干しするため、竹の棒で物干しのような「おだ」を組み、稲穂を下にして架けていきます。おだ掛けされた田んぼは、まるで稲のカーテンがかけられたような美しい光景となりました。
稲刈りの後には、稲から籾を取る脱穀作業も体験しました。足踏み脱穀機と千歯こきを使い、昔ながらの方法を学びました。
この後、稲は4日から5日ほど乾燥させ、農村公園管理組合によって脱穀され玄米になる予定です。きっとおいしいお米になることでしょう。
作業を終えた後には、農村公園特製のカレーライスをみんなで美味しくいただきました。








9月2日(火曜日)9時30分~11時50分 天候:晴れ
中川小学校 【参加人数】児童:40名 先生2名




9月3日(水曜日)8時55分~12時00分 天候:晴れ
長浦小学校 【参加人数】児童:79名、先生:6名




9月4日(火曜日)10時10分~12時15分 天候:晴れ
平岡小学校 【参加人数】児童:26名 先生:3名




9月9日(火曜日)9時00分~12時45分 天候:曇り
奈良輪小学校 【参加人数】児童:113名 先生:6名




9月11日(水曜日)8時55分~11時45分 天候:晴れ
根形小学校 【参加人数】児童:42名、先生:4名




9月7日(木曜日)12時58分~14時30分 天候:晴れ
昭和小学校 【参加人数】児童:108名 先生:6名
※9月5日(金曜日)が悪天候だったため、同日スガイナイ、脱穀、昼食を実施。稲刈りを9月7日としました。




草取り
ひらおかの里農村公園では、4月から5月にかけて市内の小学生が田植えをしました。児童たちが植えた1株3~5本の稲は、今では株が分かれて何倍にも増え、背丈も児童の股下ほどまで青々と生長しています。
稲は、この時期に草を取り、根を切ることで、より強く元気に育ちます。ひらおかの里農村公園では、手作業ではなく中耕除草機、通称「ころがし」を使って草取りを行います。
「ころがし」を稲の間に走らせると、回転する刃が草を土の中に押し込み、同時に稲の根を切ることで、稲の生長をさらに促す効果があります。
草取り作業の説明では、「稲を1列またいで歩く」、「ころがしは土の表面と水平に押す」、「腰のあたりに手を持ってきて押す」、「ころがしが重くなったら土を落とす」と伝えられました。
説明後、児童たちは田んぼに入り、両側からリレー形式で一生懸命に「ころがし」を押していました。
9月の稲刈りでは、元気な稲から美味しいお米が収穫できることを楽しみにしています。




6月5日(木曜日)9時30分~10時55分 天候:晴れ
平岡小学校 【参加人数】児童:26名、先生:3名
はじめの会では、管理組合の組合長からのあいさつの後、組合員の方々が「ころがし」の使い方について説明しました。「ころがしを押すときは水平にして腰の位置で」、「ころがしが重くなったら本体を横にして土を落として」、「進むときは稲を左右に跨いで」など説明があり、児童は真剣な表情で聞いていました。
児童たちは田んぼの両側に2つの班に分かれ、リレー形式で「ころがし」を押す作業を体験しました。一人ずつ片道を進み、交代しながら繰り返します。
組合員の方々が田んぼに入り、児童に直接、「ころがし」を押す手の位置や田んぼでの歩き方を指導しました。
中には「ころがし」がなかなか進まず苦戦する児童もいましたが、慣れてくると楽しそうに何度も往復する姿も見られました。順番を待っている児童たちは、大きな声で仲間を応援していました。
作業の後には、園内で収穫された蒸かしジャガイモが用意され、児童たちは管理棟の中で美味しそうに食べていました。


6月6日(金曜日)9時15分~10時45分 天候:晴れ
長浦小学校 【参加人数】児童:77名、先生:5名
児童たちは、3つの田んぼに分かれて、「ころがし」を使った作業を行いました。ほとんどの田んぼでは両端から、1つの田んぼでは片側から、リレー形式で「ころがし」を押していきました。全部で26台の「ころがし」があり、だいたい1台につき3人の児童が交代で使いました。
「ころがし」をうまく扱えない子には、組合員さんが田んぼの中でそばにつき、丁寧に教えていました。
「ころがし」を押す順番を待つ間、男の子たちが側溝で小さなザリガニやカエルを見つけて、楽しそうにしている姿も見られました。
作業を終えて着替えが終わると、児童たちは管理棟の軒下や屋外でグループになり、蒸したジャガイモを賑やかに食べていました。
終わりの会では、児童たちから管理組合の方々へ、感謝の言葉が伝えられました。


6月11日(水曜日)8時40分~10時10分 天候:曇り時々雨
中川小学校 【参加人数】児童:36名、先生:2名
この日は曇り空で、時折小雨がぱらつき、風も強く吹いていました。児童たちはカッパなどの雨具を持ってきていましたが、着用するほどではありませんでした。
はじめの会の後、組合員さんから作業の説明があり、児童たちは皆、熱心に耳を傾けていました。
作業中、泥に足を取られて除草機がなかなか進まず、体勢を崩しそうになる児童もいましたが、全体的には比較的スムーズに作業を進めることができました。
作業終了後には、管理組合の皆さんが蒸かしてくれたジャガイモを、児童たちはとてもおいしそうに頬張っていました。


6月12日(木曜日)9時15分~10時45分 天候:晴れ
根形小学校 【参加人数】児童42名、先生:4名
始めに、児童たちによる「田んぼの草刈り頑張るぞーの会」が開催されました。会では、組合長からのあいさつや作業の説明があり、児童たちは静かに耳を傾けていました。
作業では、児童たちが2つの班に分かれ、田んぼの両端から「ころがし」をリレー方式で押していきました。
昨年度、悪天候で実施できなかった根形小には、事前に情報が十分に伝わっていなかったため、中には手で草刈りや草むしりをすると思っていた先生もいらっしゃいましたが、全員で協力してスムーズに作業を進めることができました。
裸足で田んぼに入ることをためらう児童はほとんどいませんでした。小さなアマガエルを見つけて、そっと避けてあげる優しい女子児童の姿も見られました。
作業後には、蒸したての熱々のジャガイモ(きたあかり)を屋外(一部は室内)で食べました。敷地の端にある四阿(あずまや)まで行って食べる児童もいて、あちこちから「美味しかった!」という声がたくさん聞こえてきました。


田植え
今年で22年目を迎える「令和7年度田んぼの学校」が始まりました。本企画は、小学5年生を対象に昔ながらの方法で稲作を体験してもらうことを目的としています。今年は、コシヒカリの栽培に挑戦します。
最初に、子どもたちは田植えに挑戦しました。ひらおかの里農村公園管理組合が事前に耕し、代掻き(しろかき)を済ませた田んぼで、事前に育てておいた苗を植えていきます。植え方の説明では、まず田んぼの中では足をつま先から入れ踵から抜くこと、そして苗は根っこ部分から3~5本程度にし、親指・人差し指・中指の3本で土に中に差し込むことなどが説明されました。
最初は裸足で田んぼに入るのをためらっていた子どもたちも、次第に慣れていきました。管理組合のメンバーからコツを教えてもらいながら、熱心に苗を植えていきました。中には泥だらけになったり、尻もちをついたりする子もいましたが、作業が進むにつれて「楽しかった!」「もっとやりたい!」といった声が聞こえ、たくさんの笑顔が見られました。
田植えの後は、昔から使われている農具から現代の機械まで、その移り変わりについて説明を受けました。
鍬・まんが・鋤・中耕除草機・千把・唐み(選別)・耕運機・トラクター・田植え機・コンバインなど実際に見て触れることで、稲作の歴史と進化を学ぶことができました。
終わりの会では、子どもたちから「疲れたけど楽しかった。」「農家さんの大変さがわかった。」「お米の大切さがわかり、もっと美味しく食べるようにしたい。」等様々な感想が発表されました。
今回の体験を通して、子どもたちは稲作の苦労や喜び、そして食の大切さを実感したようです。




4月22日(火曜日)8時40分~11時30分 天候:曇り
奈良輪小学校 【参加人数】児童:113名、先生:7名




4月25日(金曜日)8時58分~10時58分 天候:晴れのち曇り
長浦小学校 【参加人数】児童:77名、先生:5名




4月30日(水曜日)8時54分~11時24分 天候:晴れ
昭和小学校 【参加人数】児童:121名、先生:7名




5月1日(木曜日)8時45分~10時35分 天候:晴れ
中川小学校 【参加人数】児童:39名、先生:3名




5月7日(水曜日)8時55分~11時00分 天候:晴れ時々曇り
平岡小学校 【参加人数】児童:25名、先生:3名




5月8日(木曜日)9時20分~11時7分 天候:晴れ
根形小学校 【参加人数】児童:44名、先生:5名