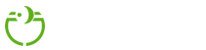本文
新しく文化財を指定しました(永吉台遺跡群出土の古代文字及び信仰関連資料群)
永吉台遺跡群出土の古代文字及び信仰関連資料群
永吉台遺跡群は平岡地区に所在し、遠寺原地区、西寺原地区の2地区で構成された遺跡群です。
発掘調査が行われた場所は、現在は東京ドイツ村の敷地内であり、多くの人でにぎわう場所です。

※地理院タイルに永吉台遺跡群を追記して掲載
発掘調査
昭和57年から昭和59年にかけて開発行為に伴う発掘調査が行われ、貴重な成果が得られました。
特筆すべきこととして、遠寺原地区からは廂のついた寺院と見られる建物跡が、西寺原地区からは土器を生産した遺構が出土し、両地区から文字が書かれた「墨書土器」、文字を書くための道具や識字層の存在を示す道具、仏教を始めとする信仰に関する資料が発見されました。

文字資料
土器の表面に墨で文字を書いた「墨書土器」のほか、粘土が乾く前にヘラで文字を書いたヘラ書土器も見つかっています。
文字の意味は不明瞭ですが、「寺」「佛」といった仏教関連、「万得」といった吉祥句、「酒二升半浄浄稲五千」といった長文も見られます。
「酒二升半 浄浄 稲五千」の多文字が書かれた土器
「寺」の字が書かれた土器
「佛」の字が書かれた土器
文字関連資料
文字に関係する資料として硯(すずり)や水滴(硯に水を注ぐ道具)も見つかっています。
硯

水滴
他にも、丸鞆(まるとも)・巡方(じゅんぽう)と呼ばれるベルトの飾りが出土しています。
当時のベルトは役人の衣装であり、書類を書く役人がいた証拠です。

丸鞆(まるとも)と巡方(じゅんぽう)
信仰関連資料
灯明皿(とうみょうざら)という油を入れて燈心に火を灯す灯具や、寺院の塔を模した瓦塔(がとう)、香炉の蓋などの仏教に関連する道具が、廂(ひさし)のついた寺院と見られる建物跡周辺から出土しました。
灯明皿(とうみょうざら)

瓦塔(がとう)
香炉(蓋)
新指定文化財「永吉台遺跡群出土の古代文字及び信仰関連資料群」
これらの発掘調査結果は、国府や郡衙でもない地方の集落に識字層が存在し、仏教寺院が存在していた事を示しています。
この事実は「村落内寺院」の名称を提示するきっかけとなり、学史的にも大きな意義があるため、出土資料158点が袖ケ浦市の文化財として指定されました。