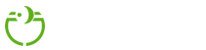本文
農業センター 講習会実施報告(2025年)






農業センターの営農指導員が講師を務める「野菜栽培講習会」は、市内で野菜作りに関心のある方を対象とした事業です。
これから野菜を始めたい方から、すでに家庭菜園を楽しんでいる方、そして就農者の方まで、様々なレベルの方にご参加いただいています。講習会では、毎回テーマを決めて、野菜作りのポイントをわかりやすく解説しています。
実施された講習会の内容をまとめた報告も掲載していますので、ぜひご覧ください。
就農者や家庭菜園をされている、これから野菜作りを始めたい方にも好評の講習会です。
野菜栽培講習会
11月11日(火曜日) 9時30分から




第11回『野菜栽培講習会』です。
今回の講習会は、保温栽培についてです。
保温栽培が可能な冬野菜について、家庭菜園で市販の資材を使って作れるのは、葉菜類ではコマツナ、ホウレンソウ、シュンギク、リーフレタスなど、根菜類ではダイコン、カブ、ニンジンなどです。保温栽培用の資材としては、トンネル用の支柱とフィルム、寒冷紗、不織布等の被覆資材などがあります。発芽促進や「とう立ち(花芽がつくこと)」防止など、高い温度が必要なときには必需品です。
「とう立ち」については、ダイコンやカブは10℃以下の状態が1ケ月続くと花芽分化してしまうので、トンネル内で栽培することにより防ぐ事が出来ます。
トンネル用の保温資材には種類があり、素材・厚み・光の透過率・耐用年数などの違いについて説明をしました。
圃場(畑)では、ブロッコリー、カリフラワー、タマネギ(苗)等の生育状況観察後、エンドウマメ(品種:キヌサヤとスナックエンドウ)の種蒔きとソラマメの定植です。
エンドウマメ2種の種蒔きのため、黒マルチに30cmを目安に穴あけ機で穴を開けます。次にゼリーなどの空き容器の底を植え穴に軽く押し当てて土をへこませ、種を4粒蒔きます。穴を埋める様に土を平にかけて軽く手で押さえて鎮圧します。
ソラマメの定植では、黒マルチに60cmを目安に穴あけ機で定植する穴を開けます。定植穴に殺虫剤を播き、10月の回で播種しポットで育成した苗を植えこみ手で押さえ鎮圧し、余分な土は泥跳ねを防ぐために払っておきます。
次に、マルチの張り方では、まず畝を平らにならし、畝がまっすぐになるように紐を張り、マルチの中心の線に合わせマルチを広げ、マルチがピンと張るように足でマルチの端を踏みながら土を寄せます。
10月14日(火曜日) 9時30分から




第10回『野菜栽培講習会』です。
資料を用いて土壌分析についての講義を行いました。
圃場(畑)の土を分析に出す際のサンプルの正しい取り方、分析項目の違い、そして必要な成分の計算方法などを学ぶことができました。これらの知識は、作付する野菜に最適な土壌環境を作るために役立ちます。
現在、土壌分析はJAや民間ホームセンターでも実施することが可能です。農業センターでは、農作物の栽培相談において、土壌分析報告書の結果に基づき、土壌診断と次作の野菜に合った施肥の処方箋(施肥設計)を出しておりますので、ぜひご活用ください。
講義の後には、ビニールハウス内でソラマメ(品種:陵西一寸と千倉一寸)をポットに蒔く作業を実習しました。ソラマメの種を蒔く際は、オハグロ(種にある黒い筋で、根が出る部分)を下向きにし、種の半分から3分の2程度が土に埋まるように注意して蒔きます。種まきを終えたポットは育苗かごに並べ、たっぷりと水を与えました。
今後、このポットでソラマメを育苗し、発芽して本葉が5枚ほどになった段階で、圃場へ定植する予定です。
最後に、圃場内のキャベツ、白菜、ブロッコリー、菜花、大根、らっきょう、にんにく、アスパラ、タマネギなどの多様な作物の育成状況を観察しました。
9月30日(火曜日) 9時30分から


第9回『野菜栽培講習会』では、資料を用いてソラマメとサヤエンドウの栽培方法について詳しく講義を行いました。
ソラマメは、冬の寒さに当たることで花芽を分化させ、春に実をつける野菜です。栽培にあたっては、酸性土壌を嫌うためpH調整が必要です。また、連作を嫌うため、前作でマメ科の作物を栽培した場所は避けます。
種まきは、まず9cmポットを使用します。種にあるオハグロ(黒い筋、根が出る部分)を下にして蒔き、育苗します。本葉が2〜3枚になったら、11月上旬から中旬に畑へ定植します。畑に直接種を蒔かずポットで育苗するのは、発芽率の悪さや、発芽しなかった場合の株間の開きを防ぐためです。また、カラスによる食害を防ぎ、高価な種の無駄を防ぐという利点もあります。
生育が進むとアブラムシが付きやすいため、反射マルチなどでの対策が有効です。
サヤエンドウもまた連作を嫌うため、マメ科の植物を栽培した場所は避ける必要があります。排水の良い土壌を好み、水はけを良くするためにできるだけ高畝にして栽培します。
種まきは10月下旬から11月中旬が目安です。あまり早く蒔き過ぎると育ち過ぎてしまい、厳冬期の霜に当たって枯れる可能性があるため注意が必要です。霜から守るために笹の葉やネットで霜除けをします。種は1ヶ所に3粒から5粒を蒔き、株間は30cm取ります。間引きはせず、春になったら支柱立てと誘引を行います。
講義の後は、圃場内のカリフラワー、白菜、タマネギなどの育成状況を観察しました。
圃場実習では、大根の間引き作業と、5月に植え付けたサツマイモ「シルクスイート」1畝の掘り上げを行いました。
9月16日(火曜日) 9時30分から


第8回『野菜栽培講習会』です。
今回の講習会では、ホウレンソウ・コマツナの栽培方法やサツマイモと落花生について学びました。
ホウレンソウには、日本在来種(東洋種)と西洋種があります。在来種は味が良く根元の赤みが強いのが特徴です。一方、西洋種は密植栽培が可能で種まき時期が長いという利点がありますが、アクが強いとされています。最近では、それぞれの良い性質を兼ね備えた品種や、べと病に強い品種も多く栽培されています。
コマツナの種まきは3月から10月が適しています。暑さや寒さに比較的強く、真冬を除けばほぼ一年中栽培でき、約40~50日で収穫できます。ホウレンソウに比べると酸性土壌に強いですが、連作障害が出るため、収穫後は1~2年空けるのがおすすめです。ホウレンソウとコマツナは、どちらもプランターで栽培する場合、水やりによって土の肥料分が流れてしまうため追肥が必要です。
サツマイモのイモが小さくなるのは、肥料が多すぎて「つるぼけ」を起こした可能性があります。苗を植えてから約120日が収穫の目安です。試し掘りをして収穫時期を判断しましょう。サツマイモは、収穫後すぐに食べるよりも、2〜3週間保存することでデンプンが糖化し、甘みが増すと言われています。
圃場実習では、大根と落花生の作業を行いました。
大根の種まきは、畝間を60〜75センチメートル、株間を30センチメートルあけて1箇所に3粒ずつ種をまきました。
その後、落花生「おおまさり」の収穫を行いました。
8月5日(火曜日) 9時30分から


第7回『野菜栽培講習会』です。
今回の講習会では、資料を使いながらタマネギの栽培方法を学びました。タマネギの種や苗には、秋に種をまく早生、中生、中晩生といった品種があり、それぞれまく時期や長期保存できるかなどが異なるため、事前に確認が必要です。
一般的に、種まきは彼岸の頃にあたる9月が目安です。タマネギは酸性の土壌が苦手でアルカリ性を好むため、種まきの1か月前には石灰をまいて土壌を調整しておく必要があります。苗を育てるには約2か月かかるため、畑への植え付けは11月中旬ごろになります。中生種のタマネギの場合は、10月上旬までに種をまき、11月下旬から12月上旬に畑に植え付けます。
畑に苗を植える際は、白い部分の半分が土に埋まるように植え付けましょう。タマネギの苗は冬の間に成長が緩やかになるため、この時期の追肥のしすぎには注意が必要です。
次に、畑でニンジンの種まきを行いました。平らに整地された畝に、細長い棒で深さ1cmほどの浅い溝を作り、全員で種をまきました。種の上に薄く土をかぶせて軽く押さえつけます。近年は暑い日が続いているため、土壌の乾燥を防ぐためにワラを敷くなどの対策が有効です。
その後、ナス、トマト、オクラ、ピーマン、パプリカ、キュウリの収穫体験を行いました。
また、枝豆、ネギ、落花生、サトイモの生育状況も観察しました。
7月18日(金曜日) 9時30分から


第6回『野菜栽培講習会』では、秋野菜の栽培準備について学習しました。
厳しい暑さが続くので、8月下旬からの種まきに備え、今から準備を進める必要があります。
座学では資料に基づき、各野菜の品種や種まき時期、肥料、病害虫対策などを詳しく説明しました。
キャベツの品種は「夏播き秋冬採り(初恋、YR金春)」と「秋播き春採り(金系)」の2種類に大きく分けられます。名前に「YR」とあるものは病気に強い品種です。また、育苗については、できるだけ大きな苗を育てると良いでしょう。
ブロッコリーの種を選ぶ際は、早生種・中生種・晩生種のいずれかを確認することが重要です。花芽が分化する時期と気温を意識して管理するよう説明がありました。風に弱いため、追肥後に土寄せをすると効果的とのことです。
ハクサイの発芽に適した温度は18℃から22℃です。猛暑が続く場合は、種まきから育苗までが難しいため、苗の購入を推奨するとのことでした。品種名に数字(例:○○60)が入っているものは、定植から収穫までの日数を示しており、60日後に収穫できるという意味です。また、結球期に気温が高いと丸まらないことがあるため注意が必要とのことでした。
ダイコンでは、秋に種をまき、年内に収穫する品種は、約2か月で収穫できます。土に石などの硬いものがあると、根が曲がったり、二股に分かれたりする原因になります。他の野菜に比べて肥料は少なくて大丈夫だそうです。
ニンジンは種をまいて芽が出れば、半分成功したといえるほど発芽が難しい野菜です。もし芽が出なかった場合でも、8月下旬までにまき直すことができるとのことでした。
ジャガイモは、9月に植えると、年内に新ジャガを収穫できます。病気の種イモを避けるため、自分で作ったイモではなく購入した種イモを使うことを推奨するそうです。種イモは芋の大きさによって半分や4つに切って植えますが、夏場は腐りやすいため、切らずにそのまま植えるのが良い方法とのことでした。
栽培全般の注意点として、秋野菜は種をまく時期を守らないと、栽培が難しくなります。また、害虫や台風の対策として、寒冷紗などの防虫・防風ネットを上手に活用するようアドバイスがありました。
実習ではナスの更新剪定を行いました。ナスのほか、トマト、ピーマン、パプリカ、オクラ、キュウリ、枝豆の収穫も体験しました。
7月2日(火曜日) 9時30分から


第5回『野菜栽培講習会』です。
今回は、まず資料を用いたナスの剪定に関する講義を行いました。その後、畑に移動して夏野菜の栽培管理実習を実施しました。
ナスの側枝剪定には、主に2つの方法があります。
1つ目は収量重視の場合で、枝葉をそのまま伸ばし、育ったナスを収穫していく方法です。7月後半に株が疲れてくるため、「更新剪定」を行うことで、8月のお盆の頃から秋ナスを収穫できるようになります。
2つ目は品質重視の場合で、「切り戻し剪定」を行います。これは、側枝に花が咲いたすぐ上の葉を残して摘芯し、花の上とすぐ下のわき芽は取り除き、1つだけわき芽を残す方法です。実がなったら、そのすぐ下の部分で剪定します。
当センターでは、秋までナスを収穫するため、「切り戻し剪定」を採用しています。そのため、畑での実習では、営農指導員が「切り戻し剪定」をメインに説明を交えながら実演し、その後受講生の皆さんに剪定実習を行いました。
最後に、トマトの芽かきと、ネギ、枝豆、サツマイモ、サトイモの生育状況を観察しました。その後、ピーマン、オクラ、キュウリを収穫して今回の講習会を締めくくりました。
6月6日(金曜日) 9時30分から


第4回『野菜栽培講習会』です。
まず夏野菜であるトマト、ナス、キュウリの仕立て(整枝)と栽培管理、そして連作障害について講義を行いました。
トマトは、基本的に1本仕立てとし、わき芽は小さいうちに摘み取ることが重要です。
ナスは、最初の実のすぐ下にあるわき芽2つと主枝の合計3本を伸ばす3本整枝を推奨しています。また、キュウリは節成り型にするため、下から5節目までの雌花とわき芽は摘み取り、子づるは1〜2節残して摘芯します。
連作障害は、病害虫の増加や土壌養分の偏りが主な原因です。この問題を避けるためには、コンパニオンプランツを混ぜて植えたり、間作として利用したり、障壁として植える方法があります。さらに、畑をいくつかの区画に分け、科ごとに野菜を割り振って順番に栽培していく「輪作」も有効な対策です。
講義の後は、圃場での実習を行いました。実際に栽培している野菜を使って、仕立てや芽かき(わき芽の摘み取り)の方法を説明し、実践していただきました。これらの作業は、野菜の生育中に繰り返し行うことで目が慣れ、どの芽やツルを取り除くべきかが自然とわかるようになります。
5月13日(火曜日) 9時30分から


第3回『野菜栽培講習会』です。
座学として、はじめにサツマイモの栽培に関する説明があり、苗の植え方について説明がありました。
次に、化学農薬を使わない病害虫防除の一環としてコンパニオンプランツについても解説がありました。
座学に続いて、圃場で苗植えを行いました。今回は「紅あずま」と「シルクスイート」の2種類のサツマイモを2回に分けて植え付けました。均一な収穫を目指し、「船底植え」を採用しました。また、今後の圃場での風向き(南寄りの風)を考慮し、根を南側、生長点を北側に向けて斜めに植え付けました。
苗植えの他に、ジャガイモ「きたあかり」、ニンジン、タマネギ、紫タマネギ、ニンニク、ダイコンなどを収穫しました。
5月2日(金曜日) 9時30分から


第2回『野菜栽培講習会』です。
座学では、マルチの種類と特性、張り方について、講義が行われました。マルチフィルムは、低温期用と高温期用があり、それぞれの特性に合わせて使い分けることが重要であること、きれいに張るコツは事前に畝(うね)の表面を平らにならしておくことなどの説明がありました。
次にトマト、ナス、キュウリなどの栽培について講義が行われました。これらの作物は連作障害を起こす可能性があるため、同じ場所での栽培は3年から5年ほど間隔をあけるのが好ましいこと、ジャガイモの後の畑も避けるよう説明がありました。
実習は、トマトの定植を行いました。トマトは、花が茎の同じ側に付くという特性があるため、植え付け時に花の付いている方向を揃えておくと、後で収穫作業がしやすくなること、苗を添え木に結び付ける際は、苗と添え木の間にひもをクロスさせ、苗にダメージを与えない程度に緩めに結ぶことなどの説明がありました。
その後、圃場内のジャガイモ、トウモロコシなどの生育観察をし、受講生の皆さんでダイコンなどを収穫しました。
4月15日(火曜日) 9時30分から


農業センターにて今年度1回目となる「初心者向け野菜栽培講習会」が開催されました。
当日は晴天に恵まれ、19名の受講生が参加しました。
開講式では、受講生の皆さんが野菜栽培を学ぶ目的を共有しました。「家庭菜園で野菜作りをしているので一から勉強したい」「おいしい野菜をつくって、野菜嫌いな子供に食べさせたい」「親から引き継いだ農地を有効活用したい」といった意欲的な声が聞かれました。
その後、資料を用いて「良い土と酸性土壌の特徴」、「植物に必要な要素(5大要素、3大要素、微量要素)の働き」、「化学肥料と有機肥料の特徴」、「野菜の特性」、「トウモロコシの栽培方法」について講義が行われました。
講義後は、ほ場(畑)やハウスに移動し、現在栽培中のエンドウ、ダイコン、トウモロコシ、タマネギ、ニンニク、ジャガイモなどを見学しながら、それぞれの野菜について説明を受けました。
本講習会は年間を通して14回、平日の火曜日に開催される予定です。
次回からは実技演習も行い、より実践的な内容となる予定です。
果樹栽培講習会
本講習会は年間3回開催され、今年度も高校で果樹栽培の指導経験をお持ちの前田先生を講師にお招きしています。ここでは、実施した講習会の内容を簡単にご紹介します。
6月17日(火曜日)9時30分から




この日の出席は、20名中18名でした。
開講式では農林振興課長が挨拶し、講師紹介、注意事項・次回以降の予定を説明しました。
続いて、受講生の自己紹介では現在栽培している果樹、今後栽培したい果樹、講習会で学びたいことなどの発表がありました。
自己紹介後、座学を実施しました。
まずは、「落葉果樹の苗木の定植後の管理」については、苗木を植えた後、地面から50〜60cmの高さで幹を切り、3本仕立てを基本として樹形を整えることが推奨されるとの説明がありました。また、リンゴ、ナシなどは日光がよく当たるよう盃状型に樹形を整えるとのことでした。
次に「果樹栽培の基礎・樹種別果樹の管理作業」について、落葉果樹の年間生育表を用いて、「4つの成長のステージ」「1年の生育サイクル」「栄養成長と生殖成長のバランス」について説明がありました。
「樹種別果樹の管理作業」では、カキ、ウメ、ナシ、イチジク、ブドウなど、樹種ごとの管理作業について具体的な解説がありました。
座学終了後、ほ場に移動し、ウメ、カキ、ブルーベリー、ミカン、ブドウ、イチジクなどの実際の果樹を見ながら、剪定や摘果などについて実践的な説明が行われました。