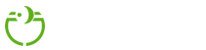本文
住居確保給付金について
住居確保給付金とは
住居確保給付金には、二つの種類の給付があります。
(1)家賃補助
離職等の理由により、住居を失った方または住居を失うおそれのある方に対し、自立相談支援機関(自立相談支援室「そでさぽ」)の支援を受けて、就職活動を行うことや収入要件などを条件に、原則3か月間(要件を満たす場合延長あり)、家賃相当額を支給するもの。
(2)転居費用補助
同一の世帯に属する方の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し住居を失った方または住居を失うおそれのある方に対し、自立相談支援機関(自立相談支援室「そでさぽ」)の支援を受けて、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居することにより、家計全体の支出が改善されると認められた場合、収入要件などを条件に、転居費用相当額を支給するもの。
対象となる方
(1)家賃補助
(2)転居費用補助
※自立相談支援機関(自立相談支援室「そでさぽ」)の支援を受けて、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居することにより家計全体の支出が改善されると認められる必要があります。
収入基準額(家賃補助・転居費用補助 共通)
| 世帯人数 |
収入基準額(上限) |
算定方法(基準額+家賃額) |
|---|---|---|
| 1人 | ~115,200円 | 78,000円+家賃額(上限37,200円) |
| 2人 | ~160,000円 | 115,000円+家賃額(上限45,000円) |
| 3人 | ~188,400円 | 140,000円+家賃額(上限48,400円) |
| 4人 | ~223,400円 | 175,000円+家賃額(上限48,400円) |
| 5人 | ~257,400円 | 209,000円+家賃額(上限48,400円) |
| 6人 | ~294,000円 | 242,000円+家賃額(上限52,000円) |
| 7人以上 | ~333,100円 | 275,000円+家賃額(上限58,100円) |
金融資産額(家賃補助・転居費用補助 共通)
| 世帯人数 | 預貯金等の額+現金 |
|---|---|
| 1人 | 468,000円以下 |
| 2人 | 690,000円以下 |
| 3人 | 840,000円以下 |
| 4人以上 | 1,000,000円以下 |
支給について
(1)家賃補助
家賃額のうち、以下の表の額を上限として、収入に応じて調整された額を原則3か月間支給します。
受給決定後は、6か月以上の期間または期間の定めのない就職に向けて、次の活動を行っていただきます。
(1)月4回以上、自立相談支援室「そでさぽ」の面談等の支援を受ける
(2)月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
(3)原則、週1回以上求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受ける
一定の要件を満たせば、3か月間の延長が2回可能となり、最長9か月間支給が受けられます。また、一定の要件を満たせば、再支給を受けられる場合もあります。共益費・管理費等は支給対象外です。
| 世帯人数 | 支給額(上限) |
|---|---|
| 1人 | ~37,200円 |
| 2人 | ~45,000円 |
| 3~5人 | ~48,400円 |
| 6人 | ~52,000円 |
| 7人 | ~58,100円 |
(2)転居費用補助
転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じた額を上限とし、転居費用相当額を支給します。
住宅扶助基準に基づく額は自治体によって異なりますが、袖ケ浦市への転居の場合は、以下の表の額が支給上限額となります。
| 世帯人数 | 支給額(上限) |
|---|---|
| 1人 | 111,600円 |
| 2人 | 135,000円 |
| 3~5人 | 145,200円 |
| 6人 | 156,000円 |
| 7人 | 174,300円 |
※敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費等は対象外です。
※事前に自立相談支援機関(自立相談支援室「そでさぽ」)の支援を受けて、家計改善支援事業による家計の見直しを行い、転居することにより、家計全体の支出が改善されると認められる必要があります。希望する転居先の住居の家賃が、家計の改善が見込めない家賃額であると判断する場合は、必要に応じて、別の物件を探していただく場合があります。
申請について
まずは、自立相談支援室「そでさぽ」にお問い合わせください。
相談員が住居確保給付金を含め、そのほかの支援を検討します。
連絡先:0438ー53ー8840(直通)
相談時間
毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分